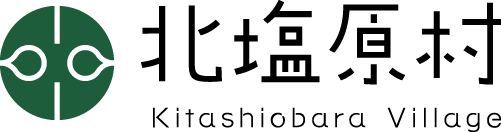本文
介護保険料について
介護保険の財源は、公費(税金)と保険料(40歳以上の方)で支えられています。
それぞれの負担割合は公費(国、県、市)の割合が50%、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料が23%、第2号被保険者の保険料(40歳から64歳の方)が27%となっています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
第1号被保険者の介護保険料は、北塩原村の介護サービス費用がまかなえるよう決定した「基準額」をもとに、前年の所得に応じた負担段階を設定しています。
令和6年度から令和8年度までの北塩原村の介護保険料は以下のとおりです。
|
段階 |
世帯区分 |
対象者 |
保険料基準率※2 |
保険料年額 |
|---|---|---|---|---|
|
第1段階 |
非課税世帯 ※1 |
(1)生活保護被保護者 (2)老齢福祉年金受給者 (3)本人の年金収入等が80万円以下 |
0.285 |
22,900円 |
|
第2段階 |
本人の年金収入等が80万円超120万円以下 |
0.485 |
38,900円 |
|
|
第3段階 |
本人の年金収入等が120万円超 |
0.685 |
55,000円 |
|
|
第4段階 |
課税世帯 ※1 |
本人の住民税が非課税かつ年金収入等が80万円以下 |
0.9 |
72,300円 |
|
第5段階 |
本人の住民税が非課税かつ年金収入等が80万円超 |
1.0 (基準率) |
80,400円 (基準額) |
|
|
第6段階 |
本人の合計所得が120万円未満 |
1.2 |
96,400円 |
|
|
第7段階 |
本人の合計所得が120万円以上210万円未満 |
1.3 |
104,500円 |
|
|
第8段階 |
本人の合計所得が210万円以上320万円未満 |
1.5 |
120,600円 |
|
|
第9段階 |
本人の合計所得が320万円以上420万円未満 |
1.7 |
136,600円 |
|
|
第10段階 |
本人の合計所得が420万円以上520万円未満 | 1.9 | 152,700円 | |
|
第11段階 |
本人の合計所得が520万円以上620万円未満 | 2.1 |
168,800円 |
|
|
第12段階 |
本人の合計所得が620万円以上720万円未満 | 2.3 | 184,900円 | |
|
第13段階 |
本人の合計所得が720万円以上 | 2.4 | 192,900円 |
※1 世帯区分について
非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税の世帯のことをいいます。
課税世帯とは、世帯に住民税課税の方が1名以上いる世帯のことをいいます。
なお、非課税、課税世帯の判定は毎年4月1日時点の世帯状況を基に行います。
例
世帯主(非課税)、妻(非課税)、息子(課税)の場合は課税世帯
世帯主(非課税)、妻(非課税)、息子(非課税)の場合は非課税世帯
※2 保険料基準率について
保険料基準率とは、保険料算定の算定における保険料率です。
第5段階の保険料を80,400円(基準額)とし、各段階の保険料は基準額にその保険料率を乗じた金額となります。なお、100円未満は切り捨てとなります。
例
(第1段階)80,400円×0.285=22,914円(100円未満切捨てで22,900円となります)
(第10段階)80,400円×1.9=152,760円(100円未満切捨てで152,700円となります)
第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料
第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険ごとに決定します。
1人ひとりの介護保険料額は給料や所得に応じて計算されます。
40歳から64歳までの方の介護保険料額の算定方法については、加入されている医療保険にお問合せください。
介護保険料の納め方
介護保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から納めます。
例)5月1日生まれ→4月分より納付
第1号被保険者(65歳以上の方)
納め方は受給している年金の額によって、次の2通りに分かれ個人で納め方を選ぶことは出来ません。
特別徴収
介護保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて天引きになります。
4月・6月・8月は、仮に算定された保険料を納め(仮徴収)、10月・12月・2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納めます(本徴収)。
※特別徴収(年金からの天引きによる徴収方法)への切り替えは、対象者として要件を満たす場合、自動的に切り替わりますので手続きの必要はありません。
※普通徴収(納付書払い、または口座振替)となる場合
- 65歳到達年度
- 年度途中で介護保険料が増額になった
- 年度途中で各種年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市町村から転入した
- 介護保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになった
など
普通徴収
特別徴収以外の方は、納付書などで個別に納めていただきます。保険料の年額を年6回に分けて納めます。
納期限は7月・8月・9月・10月・12月・1月の末日となります。
(納期限が、休・祝日の場合は翌営業日になります)
村から納付書を送付しますので、役場本庁、裏磐梯合同庁舎、以下の取扱金融機関で納めていただきます。
取扱い金融機関
- 会津よつば農業協同組合
- 東邦銀行
- 福島銀行
- 大東銀行
- 会津信用金庫
※ゆうちょ銀行で納入する際には、納付書とは別に払込用紙が必要となります。
払込用紙を送付しますので、住民税務課までご連絡ください。
口座振替をご利用ください
納め忘れがないよう、便利な口座振替をご利用ください。
介護保険料の納付書、通帳、通帳の届出印をご用意いただき、上記の取扱い金融機関の窓口でお申し込みください。
口座振替の開始は、申込日の翌月または翌々月から開始となりますのでご注意ください。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
国民健康保険に加入している方
世帯に属している第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の人数や所得により決定し、国民健康保険税の一部として世帯主に課税になります。
職場の健康保険に加入している方
全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合など各医療保険者ごとに介護保険料率が決定され、医療分・後期高齢者支援分・介護分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
※40~64歳の被扶養者は個別に介護保険料を納める必要はありません。
保険料を滞納すると給付制限を受けます
介護保険では、自己負担が1~3割でいろいろな介護サービスが利用できますが、保険料の未納や滞納がある場合、きちんと納めている方との公平を保つため、1~3割負担で介護サービスを利用できなくなる場合があります。
介護サービスを利用するとき、一度費用の全額を自己負担することになります。自己負担した保険給付分は、申請により後日支給されます。それでも介護保険料の納付がない場合は申請後も保険給付分の一部または全額が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。
※「高額介護サービス」とは、1ヶ月に支払った介護費用が要介護度ごとに定められたサービス利用の上限(支給限度額)を超えた場合に、その差額分を村より払い戻しするサービスです。なお、支給限度額はそれぞれ異なりますので、詳しくは、保健福祉課(連絡先:23₋3113)までお問い合わせください。