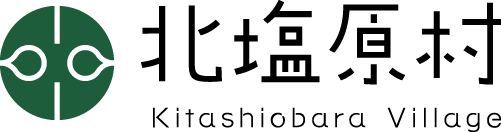本文
国民健康保険税のあらまし
国民健康保険税とは
国民健康保険加入者が医療機関などで受診するときの自己負担額は0割~3割とされており、自己負担額を除いた金額は、「国や県からの負担金」と「加入者の負担金」により賄われています。この「加入者の負担金」にあたるものが国民健康保険税です。
国民健康保険税は、国民健康保険事業に要する費用に充てる「医療給付費分」、後期高齢者医療制度を支援するための「後期高齢者支援金分」、介護保険の負担金に充てる「介護納付金分」の3つを合計したものとされており、加入者の前年中の所得や人数などを基に世帯ごとに算定します。
※ 介護納付金分は40歳~64歳までの方のみ該当します。
国民健康保険に加入する方
我が国は「国民皆保険制度」とされており、国民は何らかの形で公的医療保険に加入しなければなりません。そのため社会保険や共済組合などに加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。(国民健康保険法第5条、第6条)
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険は未成年者や乳幼児であっても、ひとり一人が被保険者(加入者)となるため、国民健康保険税の納税義務者は原則住民票上の世帯主となります。
また、世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、納税義務者は世帯主となります。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、医療分・支援分・介護分で構成され、それぞれの税額は、所得割・均等割・平等割を合算した合計となります。
令和7年度の国民健康保険税率(税率は毎年6月に決定しています。)
|
項目 |
内容 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
|---|---|---|---|---|
|
所得割 |
課税所得に対する課税額 |
6.51% |
2.68% |
2.24% |
|
均等割 |
被保険者1人あたりの額 |
28,300円 |
11,500円 |
11,300円 |
|
平等割 |
1世帯あたりの額 |
18,800円 |
7,700円 |
5,700円 |
|
課税限度額 |
1世帯における課税の上限額 |
66万円 |
26万円 |
17万円 |
国民健康保険税の計算方法
|
区分 |
計算 |
|---|---|
|
所得割 |
(前年中の所得金額※1-基礎控除43万円※2)×所得割率 ※1 所得金額調整控除がある場合には、控除後の金額 |
|
均等割 |
均等割額×被保険者数 |
|
平等割 |
平等割額×1世帯 |
※所得割、均等割、平等割の合計が国民健康保険税になります。
※月末時点で国民健康保険に加入していれば、その月の分が課税されますので、年度途中の加入脱退については月割りで計算します。
※所得割額は1人ずつ計算し、所得がマイナスとなっても他の方の所得とは通算されません。
※北塩原村では、1年間分(4月から翌年3月分)の国民健康保険税を7月に決定し、年6回(7月、8月、9月、11月、12月、1月)で納付いただいております。
※世帯の国保加入者が、65歳以上の方のみの場合には特別徴収(年金からの天引き)により納付いただいております。対象者は、自動で特別徴収に切り替わりますので手続きの必要はありません。
国民健康保険税の軽減措置について
世帯主と加入者の前年中の所得額が以下の場合、医療分、支援分、介護分のそれぞれの均等割、平等割が軽減されます。
国保税の軽減制度の詳細
|
軽減率 |
適用条件 |
|---|---|
|
7割 |
世帯合計所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
|
5割 |
世帯合計所得が43万円+(30万5千円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
|
2割 |
世帯合計所得が43万円+(56万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
|
未就学児にかかる均等割の軽減 |
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前にある方)に係る均等割額(1人あたりの額)の5割が減額となります。上記の所得額による軽減が適応されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減後)の額から5割軽減となります。 |
非自発的失業による軽減
非自発的失業(勤め先の倒産などにより失業)をされた方は、申請により軽減を受けることができます。