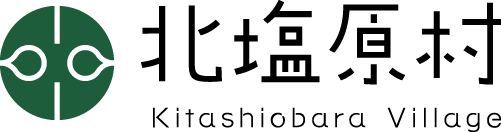本文
相続登記の義務化について
令和5年4月から所有者不明土地(※1)の解消に向けて、不動産に関するルールが変わります。
所有者不明の土地の発生予防と、すでに発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
(※1)所有者不明土地とは、次の1・2のいずれかの状態になっている土地をいいます。
- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
相続登記の申請の義務化について(令和6年4月1日施行)
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない理由として、これまで相続登記の申請は任意とされ、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間をかけてまで登記の申請をする意欲が湧きにくいことが指摘されてきました。
相続登記がされないと、登記簿の情報が古いままとなり、この状態が続き長年放置されることが所有者不明土地増加の一因となっていました。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するため、相続登記の申請が義務化されました。
これにより相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内(※2)に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がなく申請の義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
(※2)「被相続人の死亡を知った日」ではなく「その不動産を取得したことを知った日」です。
詳細およびその他の制度は法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ<外部リンク>
相続人申告登記について(令和6年4月1日施行)
登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、すべての相続人を把握するための戸籍証明書等の資料は必要ありません。
相続土地国庫帰属制度について(令和5年4月27日施行)
所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、今後その土地を利用する予定がない場合、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。
申請について
- 相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人であれば申請可能です。
- 売買等によって任意の土地を取得した場合や法人は対象外です。
- 共有地の場合は、共有者全員で申請が必要です。
対象となる土地
通常の管理または処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。要件の詳細については今後定められる予定です。申請後、法務局職員等による書面審査・実地調査が行われます。
国庫帰属が認められない場合
- 建物、車両がある土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 危険な崖がある土地
- 境界が明確でない土地
- 通路など他人による使用が予定されている土地
費用について
申請時に審査手数料の納付のほか、承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。具体的な金額は今後定められる予定です。
詳細およびその他の制度は法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ<外部リンク>
所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)
登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。
住所等の変更登記の申請義務化(令和8年4月までに施行)
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、これまで住所等の変更登記の申請は任意とされ、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されてきました。
そこで、相続登記の申請の義務化と同様に、所有者不明土地の発生を予防するため、住所等の変更登記の申請が義務化されました。
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。
なお、正当な理由がなく申請しなかった場合は、5万円以下の過料が科せられることがあります。