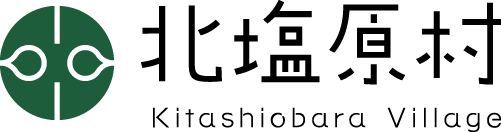本文
固定資産税について
固定資産税は、住民税とともに市町村財政を支える基幹税です。応益原則に基づき、資産価値に応じて所有者に対し課税されます。
課税の対象
1月1日時点で村内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方が課税の対象となります。
その方が所有する資産の種類毎(土地、家屋、償却資産)に課税標準額(課税の対象となる額)を算出し、課税額を決定します。
1月1日時点の現況に応じて課税するため、1月2日以降に土地や家屋を売却(所有権移転登記)したり、家屋を取り壊した場合も、その年度は1月1日時点の所有者へ課税されます。
課税額の計算
課税額の算出
以下の計算式によって課税額を算出します。
固定資産税額=(土地の課税標準額+家屋の課税標準額+償却資産の課税標準額)×税率(1.4%)
免税点について
課税標準額については、所有する資産の種類毎(土地、家屋、償却資産)に合算して算出しますが、算出した課税標準額が一定額(免税点)未満の場合、その資産については課税の対象としない(課税標準額を0円として扱う)仕組みがあります。
| 資産種類 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
例
土地の課税標準額: 25万円
家屋の課税標準額:300万円
償却資産の課税標準額:0円
課税標準額合計(土地 0円+家屋300万円+償却資産0円)×1.4%=固定資産税額4万2千円
評価額・課税標準額について
土地
土地の不動産価値を評価し算定した価格を基に、固定資産評価額と課税標準額を算出します。
固定資産評価額
固定資産評価額には、土地の不動産鑑定価格の約7割の価格が設定されます。
土地の固定資産評価額は、その土地の現況地目に応じて算出・設定されるため、登記地目とは必ずしも一致しません(登記地目は雑種地でもその土地に家屋が建っていれば宅地として扱う等)。
土地の売買取引が頻繁に行われたり、需要の変化等があればそれに伴い評価額も変動します。
特に宅地はその他の地目よりも変動が多く、地価公示価格、都道府県地価調査価格、不動産鑑定士による評価価格を参考に見直しが行われます。このように評価額の見直しを3年に一度行う制度があります(評価替え)。
課税標準額
田や畑など、宅地以外の地目は、基本的にはこの固定資産評価額と同じ額が課税標準額に設定されます。
宅地については、その土地に住宅(居住用のみ、別荘や事務所は除く)が建っている場合、200平米までの土地の課税標準額を固定資産評価額の1/6とし、200平米を超える部分の一部を1/3とする制度(住宅用地に対する課税標準の特例)等があります。
このように、土地の課税標準額については、その土地に特例制度の適用があればそれを反映した金額が設定されます。
家屋
家屋の固定資産評価額は、その家屋の再建築価格(評価時点で再度建築するとした場合に必要となる建築費)等を基準に算出されます。
家屋についても3年に一度評価額の見直し(評価替え)が行われます。
固定資産評価額・課税標準額
家屋の固定資産評価額は以下の計算式によって算出します。家屋の課税標準額は固定資産評価額と同じ金額となります。
固定資産評価額(課税標準額)=評点数(ア)×評点一点あたりの単価(イ)
(ア)評点数=再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率×需給事情による減点補正率
再建築費評点数
固定資産評価基準(全国共通の基準)に則り、その家屋の素材、面積、付帯設備、構造等を点数化したもの。
新築時(職員による家屋評価時)に算出します。3年に1度、建築物価の変動の反映を行います(評価替え)。
損耗の状況による減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗を反映する経年減点補正率、積雪等によって生ずる消耗を反映する積雪・寒冷補正率(すべての木造家屋、特定の構造の非木造家屋のみ適用)など。
経年減点補正率は家屋の構造や種類によって異なり、積雪・寒冷補正率は市区町村単位に設定されます。
需給事情による減点補正率
建築様式が著しく旧式の家屋(草葺の家屋など)や最近の生活様式に適応しない家屋など、特別な場合に個別に設定される補正率です。
(イ)評点一点あたりの単価
東京都を基準にした物価水準の地域格差を考慮した補正率と、設計監理費等の補正率を踏まえ設定されます。
新築家屋の減額措置
新築家屋については、家屋の固定資産税額を一定期間減額する制度があります。
対象となる家屋は専用住宅(一般的な自宅)や併用住宅(民宿やペンションなど、事業用と居住用を兼ねる住宅)で、床面積が50平米以上280平米以下の建物です。
併用住宅の場合は居住部分が建物の2分1以上を占めるものに限られます。
減額される税額は、減額対象範囲(建物の床面積120平米部分まで)に係る税額の2分の1です。
減額措置の適用期間は一般の新築住宅の場合は3年間、長期優良住宅(別途村への申告が必要)の場合は5年間になります。
償却資産
個人・法人の事業用資産に対する課税です。
事業者は、毎年1月1日時点で自身が村内に所有する(リースは含まない)償却資産を、1月末日までに村へ申告しなければなりません。
なお、固定資産税における償却資産の取り扱いは、国税の取り扱い(法人税、所得税の申告における減価償却資産)とは異なります。
申告の対象となる資産
- 構築物(広告塔、舗装路面、フェンス、カーポート、基礎のない建物など)
- 機械および装置(工作機械、農業用機械、施盤、ポンプなど)
- 船舶(ボート、屋形船など)
- 航空機(ヘリコプターなど)
- 車両および運搬具(大型特殊自動車、フォークリフト、構内運搬車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコン、机、椅子、ロッカー、コピー機、冷暖房機など)
- 建物附属設備(家屋として課税されているものを除く)
※耐用年数を経過している(減価償却済み)資産であっても、申告しなければなりません。
一時的に使用を休止しているなどの場合でも、資産を処分(廃棄・譲渡など)しない限りは課税の対象となります。
申告の対象とならない資産
- 土地、家屋(償却資産ではなく土地、家屋として課税されているもの)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの(トラクター、コンバインなどの小型特殊自動車も含む)
- 無形減価償却資産
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入された少額償却資産
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却する一括償却資産
※5、6について、個別の資産毎の耐用年数により減価償却を行っているものは除く
固定資産評価額・課税標準額
取得してから初回申告となる資産(前年中に取得した資産)の場合、以下の計算式によって算出します。
資産を取得した月に関わらず、半年分を償却します。
評価額(課税標準額も同額)=取得価額×(1-減価率/2)
取得してから2回目以降の申告となる資産(前年より前に取得した資産)の場合、以下の計算式によって算出します。
評価額(課税標準額も同額)=前年度の評価額×(1 -減価率)
※評価額の下限は取得価額の5%となります。上記算出の結果、それを下回る場合は取得価額の5%を評価額へ設定します。したがって、耐用年数を過ぎた資産でも所有している限りは取得価額の5%が残り続けます。
減免制度について
以下のいずれかに該当する場合、申請により固定資産税が減免される制度があります。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者(生活保護受給者)の所有する固定資産
- 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 村の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
固定資産税減免申請書(82号様式) [PDFファイル/24KB]
参考資料
さらに詳しく知りたい場合は、令和3年度固定資産税のしおり<外部リンク>をご覧ください。
各種申請書類
○固定資産の登記名義人が死亡した場合に、相続登記までの間、固定資産税等の関係書類の受取人を指定していただくもの
相続人代表者指定届出書(地方税法第9条の2第1項) [PDFファイル/44KB]
※相続登記は別途法務局で手続きする必要があります。
○登記名義人と異なる方を納税義務者等(義務者、代表者、管理者、承継者)とする場合
○納税通知書の送付先(受取人の住所)を変更する場合
○未登記家屋(登記されていない家屋)の所有者を変更する際の届出
○家屋を取り壊した場合
※滅失登記は別途法務局で手続きする必要があります。
取り壊し後、速やかに滅失登記を行う場合は当届け出の提出は不要です(滅失登記を以って村の固定資産税の課税対象から除外します)。