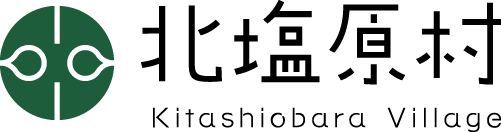本文
個人住民税(個人村県民税)について
個人住民税(個人村県民税)は、日常生活に欠かすことのできない、道路・橋梁・公共の設備から、教育、福祉、消防、救急、ごみ処理に至る様々な行政サービスに活用される税金のひとつで、個人の負担能力(所得額)に応じて課税されます。
課税される方
1月1日時点の状況が以下のいずれかに該当し、かつ前年の所得額が一定額以上の個人にその年の個人住民税が課税されます。
個人住民税の内訳は、定額の「均等割額」、前年の所得額に応じて算出される「所得割額」と国税の「森林環境税」で構成されます。さらに、「均等割」と「所得割」はその内訳として県民税(県へ納める分)、村民税(村へ納める分)があります。
- 村内に住所(住民票)を有し、村に居住している方
- 住所(住民票)は村外だが、村に居住している方
※この場合、居住の実態の判断を行い、住民票の市区町村または村のいずれかから課税されます。 - 住所(住民票)も居住も村外だが、村内に家(事務所や別荘等)を所有している方
※この場合、均等割額のみの課税(家屋敷課税)となります。
非課税となる方
1月1日時点の状況が以下のいずれかに該当する方は非課税となります。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得額が135万円以下の方
- 前年の合計所得額が、以下の計算式で求めた額以下の方
(28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1))+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族を有する場合は16万8千円)
※同一生計配偶者
生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で、前年の合計所得が48万円以下の方
※扶養親族
生計を一にする配偶者以外の親族等(事業専従者を除く)で、前年の合計所得が48万円以下の方
【例】単身世帯かつ扶養親族なしの場合
(28万円×1)+10万円+0円=38万円
【例】夫婦2人の世帯の場合
(28万円×2)+10万円+16万8千円=82万8千円
【例】夫婦2人+子ども1人(扶養親族1人)の世帯の場合
(28万円×3)+10万円+16万8千円=110万8千円
税額の算出
均等割額(定額)、前年の所得額に応じて算出される所得割額と森林環境税の1,000円を合算した額がその年度の税額となります。
均等割額
定額6,000円(村民税分3,000円+県民税分2,000円+森林環境税分1,000円)
※県民税分2,000円には、県分の森林環境税1,000円を含みます。
福島県の森林環境税と国の森林環境税の違いにつきましては、福島県のホームページをご覧ください。
「福島県森林環境税」と「国の森林環境税」について(福島県)<外部リンク>
所得割額
確定申告(給与収入のみの方は会社の年末調整)、または村への住民税申告によって確定した前年の所得金額等を基に算出します。
所得割額=課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×10%(税率)-税額控除額
所得金額
給与や年金、農業や不動産などの自営業、株式の配当や土地等の売買による収入など、収入の種類によって所得金額の算出方法は異なります。
自営業の場合は売上から経費等を差し引いた額、給与や年金の方はその収入金額によって所得金額が計算されます。
所得控除額
社会保険や生命保険、医療費などの保険料負担等に応じた控除や、配偶者や扶養親族などの扶養状況に応じた控除など、様々なものがあります。
税率
10%の内訳として、村民税分が6%、県民税分が4%です。
税額控除
所得金額や扶養状況等に応じて税額を調整(減額)する調整控除や、ふるさと納税をはじめ特定の団体等への寄付額に応じた寄附金税額控除、住宅借入金等(住宅ローン)特別税額控除などがあります。
※以下に該当する方は所得割額は0円(課税なし)となります。
前年の合計所得額が、以下の計算式で求めた額以下の方
(35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1))+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族を有する場合は32万円)
【例】単身世帯かつ扶養親族なしの場合
(35万円×1)+10万円+0円=45万円
【例】夫婦2人の世帯の場合
(35万円×2)+10万円+32万円=112万円
納税方法について
個人住民税の納付方法は、特別徴収と普通徴収のいずれか、またはその両方があります。
あくまで住民税を徴収する方法ですので、納付方法によって住民税の額が変わる事はありません。
普通徴収(現金払い)
普通徴収とは、納付書を使用して役場や指定の金融機関で納付する方法です。
納期日に口座引落としで納付する口座振替も利用できます。この場合は金融機関での手続きが必要です。
普通徴収では、住民税額を1~4期の年4回に分けて納付する形となります。
特別徴収(天引き)
特別徴収とは、給与や年金からの天引きによる徴収方法です。
給与からの特別徴収
会社が特別徴収義務者となり、支給する給与から毎月天引きして村へ納税します。
したがって、この納付方法では住民税額を各月に分けて毎月の給与から納める形となります。
給与天引きに係る手続きは、会社(給与担当者)と村の間で行いますので、ご本人が村に対して行う手続きはありません。
会社を退職した場合は天引きによる徴収が行えなくなるため、徴収方法を普通徴収に切り替えます。
会社から退職に係る通知を村へ出していただき、村側で確認後にその方の納付方法の切替を行います。
切替に伴い、村から普通徴収用(現金支払い用)の納付書をご本人へ送付しますので、以降はご自身で納付する必要があります。
○特別徴収義務者に係る届出書類等(事業主・法人向け)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/115KB]
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/27KB]
特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申告書 [PDFファイル/29KB]
特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 [PDFファイル/46KB]
普通徴収から特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/28KB]
○特別徴収義務者について
給与からの特別徴収について(平成27年~) [PDFファイル/214KB]
年金からの特別徴収
年金所得に対する住民税分を年金から天引きするものです。
この場合、年金機構と村の間で特別徴収に係るやり取りを行いますので、ご本人が村に対して行う手続きはありません。
年金からの天引き予定については、ご本人宛の年金機構からの通知に記載されておりますので、そちらをご確認ください。