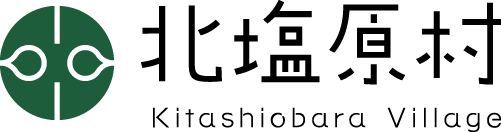本文
介護認定までの流れ
介護認定
介護保険のサービスを利用するには要介護認定の申請が必要です。
役場窓口で申請をしてください。
1 申請
護保険サービスの利用を希望する人は、役場窓口に認定の申請をしてください。
申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2 認定調査
認定調査
村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、利用者本人と家族などから聞き取り調査などをします。
主治医意見書
利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などにつての記載を受けます。
主治医がいない人は村の指定した医師の診断を受けます。
3 審査・判定
まず認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
- コンピュータによる判定(一次判定)
認定調査員が調査した調査票により、コンピュータで一次判定を行います。 - 特記事項
調査票には盛り込めない事項などを認定調査員が記載します。 - 主治医意見書
村がかかりつけ医に病気等の症状をまとめた意見書の作成を依頼します。
介護認定審査会が審査・判定(二次判定)
一次判定と、認定調査員が記載する特記事項および主治医が記載する主治医意見書をもとに、医療や福祉の専門家から構成された介護認定審査会(喜多方地方広域市町村圏組合が事務局)が総合的に審査し、要介護等の状態区分を判定します。
4 認定結果の通知
審査結果にもとづいて要介護等の状態区分に認定されます。
結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きますので、記載されている内容を確認しましょう。
平成27年8月から、介護保険の認定者に利用負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」も発行されています。
| 要介護1~5 |
生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。 介護保険の介護サービスが利用できます。 |
|---|---|
| 要支援1~2 |
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。 介護保険の介護予防サービスが利用できます。 |
| 非該当 |
生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する危険性がある人などです。 村が行う介護予防事業が利用できます。介護保険サービスは利用できません。 |
認定結果の有効期限と更新手続き
認定の有効期限は新規の場合は原則6ケ月、更新認定の場合は原則6~12ケ月です。(月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)。
また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。
要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。