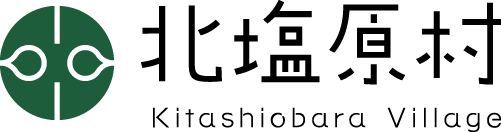本文
後期高齢者医療制度
高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、老人保健制度に代わる新しい高齢者の医療制度として、平成20年4月から始まった制度です。75歳以上の方と、一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳以上の方は、誕生(認定)日当日から被保険者となります。
後期高齢者医療制度のしくみ
福島県内のすべての市町村が加入する「福島県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営を行い、各種申請や届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務を「北塩原村」が行います。
| 福島県後期高齢者医療広域連合が行う主な業務 | 北塩原村が行う主な業務 |
|---|---|
| 保険料の決定 | 保険料の徴収 |
| 被保険者の認定・資格管理 | 被保険者の加入・脱退の届出等の受付 |
| 資格確認書の発行 | 資格確認書の引渡し |
| 医療費等の支給決定と支払 | 高額療養費、葬祭費等の給付に関する支給申請の受付 |
対象者
福島県後期高齢者医療広域連合の区域(福島県内)に住所がある次の方(ただし、生活保護受給中の方は除きます)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
- 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障がいのある方で広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から被保険者となります)
【認定を受けられる障がいの程度】
- 国民年金法による障害基礎年金の1級または2級受給者
- 身体障害者手帳1級~3級所持者
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能、言語機能、下肢障害1号、3号または4号の障がい
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者
- 療育手帳A所持者
被保険者になるとき等の必要書類
| 必要書類 | |
|---|---|
| 75歳になったとき |
手続き不要 |
| 65歳から74歳の方で障がい認定を受けるとき |
1 身体障害者手帳など障がいの状態がわかる書類 |
| 県外から転入するとき |
1 負担区分等証明書 |
| 県内他市町村から転入するとき |
1 広域内移動連絡票 |
資格確認書について
被保険者の方には「後期高齢者医療資格確認書」が1人1枚交付されます。医療機関を受診される際は、必ず資格確認書を提示してください。
75歳を迎える方には、75歳の誕生日の前月(下旬)に本人宛に郵送します。
※資格確認書の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。7月下旬に8月以降お使いいただく新しい資格確認書を郵送します。
マイナ保険証について
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します(令和8年7月31日までの暫定運用)
現在、後期高齢者医療制度における暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付する運用を行っていますが、この暫定的な運用が令和8年7月31日まで継続されることとなりました。
- 令和7年8月1日から使用できる資格確認書(オレンジ色)は、令和7年7月中に全員にお届けします。手続きは不要で、有効期限は令和8年7月31日までの1年間です。
- 資格確認書は従来の紙の保険証と同じサイズで、医療機関等で提示することで紙の保険証と同じように医療が受けられます。
- マイナ保険証を利用されている方にも資格確認書をお送りしますが、令和7年8月1日以降も引き続きマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
詳しくは、「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご覧ください。
マイナ保険証のメリット
より良い医療を受けることができます
本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも健診情報や今までに使ったことのある薬剤情報が医師等と共有することができ、より適切な医療が受けられるようになります。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除されます
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナポータルで自身の健康医療情報が確認できます
マイナポータル(※)で自身の健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が確認できます。
(※)マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
- 医療機関・薬局や市町村窓口に設置されている顔認証付きカードリーダー端末から行う
- マイナポータルから行う
- セブン銀行ATMから行う
詳しくは、「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」<外部リンク>をご覧ください。
保険料について
保険料は被保険者均等割額と所得割額の合計となり、個人ごとに計算されます。
令和7年度の賦課限度額は、80万円です。
被保険者均等割額(被保険者全員が均等に負担)
45,900円(令和6年度・令和7年度)
所得割額(所得に応じて負担)
- 賦課のもととなる所得(※)×所得割率(8.98%)
(※)賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額が控除されません。)
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて被保険者均等割額が軽減されます。
|
均等割額軽減割合 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 |
軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 7割軽減 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
13,770円 |
| 5割軽減 |
43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
22,950円 |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 36,720円 |
- 総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります。)なお、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 総所得金額等は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
- 令和7年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引きさらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。
- 年金・給与所得者の数とは、給与所得がある方(給与収入額55万円超)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和7年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満の60万円超)の数です。
- 軽減判定は、その年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険等の被扶養者であった方については、所得割額が賦課されず、被保険者均等割額が資格取得後2年間(75歳到達により加入された方は、77歳に到達する月の前月分まで、障がい認定により加入された方は、加入して24か月に到達する前月分まで)、5割軽減されます。世帯の所得が少ないことによる均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方(7割)が適用されます。
この軽減措置に申請手続きは必要ありませんが、各被用者保険等の保険者から情報提供を受けてから軽減されるため、情報提供があるまでは軽減措置を適用しない保険料を賦課することになります。なお、保険者からの情報提供が遅れる場合、申請により、被用者保険等の被扶養者であったことが確認できれば、保険料を軽減することができます。
- 被用者保険等とは
全国健康保険協会(協会けんぽ)や企業の健康保険、船員保険、共済組合のことです。市町村の「国民健康保険」及び「国民健康保険組合」は含まれません。 - 申請とは
被保険者本人が、事業主または保険者から発行される資格喪失証明書(後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であったことを証明できる書面)を提出することです。
保険料の納付について
保険料の納め方には、特別徴収(年金からの天引きによる納付)と普通徴収(口座振替または納付書による納付)があります。
特別徴収
年金から保険料を納付する方法を「特別徴収」といいます。次の1から3のすべてに該当している方が、特別徴収の対象となります。
1.年額18万円以上の年金を受給している方
2.介護保険料を特別徴収により納付している方
3.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下の方
※次のいずれかに該当する場合には、特別徴収が中止となりますのでご注意ください。
- 転出した場合
- 被保険者でなくなった場合(お亡くなりになった場合や生活保護の受給開始など)
- 年金が支給されなくなった場合 など
普通徴収
口座振替または納付書による納付する方法を「普通徴収」といいます。次のいずれかに該当している方は普通徴収になります。
- 特別徴収の要件のうち、該当しない項目がある方
- 今年度75歳になった方、または本村に転入した方
- 年度途中で保険料額が変更となった方 など
※毎年8月中旬頃に納入通知書を送付しますので、全7回で納入をお願いいたします。
口座振替をご利用ください
口座振替は、金融機関等に行かずに納付できる便利な納付方法です。仕事や家事等で忙しい方も、一度申し込みをいただくと、指定された口座から自動的に納付することができます。ぜひご利用ください。
- 取扱金融機関(口座振替が利用できる金融機関)
会津よつば農業協同組合、東邦銀行、福島銀行、大東銀行、会津信用金庫、ゆうちょ銀行 - 申し込み方法
取扱金融機関で、申込書の必要事項を記入し、通帳の届出印を押印いただき、窓口で申し込みができます。
※申込書は、役場本庁(住民税務課)、裏磐梯合同庁舎(観光課)にも備えてあります。
※金融機関の支店によっては申込書を窓口に置いていない場合がありますので、前もって住民税務課(電話0241₋23-3114)までご連絡いただけますと申込書を送付することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。
医療機関窓口での自己負担について
自己負担割合について
| 3割負担 | 村県民税の課税標準額が145万円以上の被保険者がいる世帯に属する方 |
| 2割負担 |
村県民税の課税標準額が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯で、「年金収入+その他の合計所得金額」が被保険者1人の世帯は200万円以上、被保険者2人以上の世帯は合計320万円以上の場合 |
| 1割負担 | 「2割負担」、「3割負担」の要件に当てはまらない方 |
※毎年8月1日に前年の所得等により、負担割合が見直されます。
※3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者及び70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば、1割負担または2割負担になります。
医療費の負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
外来や入院で1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請することで、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
| 世帯区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得 | 1 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】 | |
| 2 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】 | ||
| 3 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】 | ||
| 一般2 |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円※)×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円) |
57,600円【44,400円】 | |
| 一般1 | 18,000円(年間上限144,000円) | ||
| 住民税非課税世帯 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分1(年金収入80万円以下等) | 15,000円 | ||
(注)【 】内の金額は、多数回該当(直近12ヶ月に3回の高額療養費の支給<入院+外来>を受け、4回目以降の支給に該当)の場合
※医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。
医療費が自己負担額を超えた場合
高額療養費に該当された場合は、福島県後期高齢者広域連合よりお知らせが郵送されますので、申請をしてください。一度、申請により指定口座を登録すると次回以降、高額療養費に該当した場合は、自動的に登録した口座に振り込まれます。
入院したときの食事代について
入院したときは、1食あたり定められた金額を負担します。また、療養病床に入院された場合の食事代や居住費についても定められた金額を負担します。
| 世帯区分 | 食事代(1食あたり) | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得、一般(下記以外の方) | 510円 | ||
|
住民税非課税世帯 |
区分2 ※1 | 90日までの入院 | 240円 |
| 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)※3 | 190円 | ||
| 区分1 ※2 | 110円 | ||
※1 区分2…世帯全員が住民税非課税の方
※2 区分1…世帯の全員が住民税非課税かつそれぞれの所得が0円で、公的年金収入が80.67万円以下の方
※3 過去12ヶ月の入院日数のうち、世帯区分が区分2に該当する期間が超えた場合、改めて申請が必要となります。
| 世帯区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得、一般(下記以外の方) |
510円 ※1 |
370円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 区分2 | 240円 ※2 | 370円 | |
| 区分1 | 140円 ※3 | 370円 | ||
| 区分1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 | ||
療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
※1 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合です。それ以外の場合は470円です。
※2 医療の必要性の高い方について、その月を含めた過去12ヶ月間の入院日数が91日以上の場合は、190円になります。75歳になられた方や転入などにより新たに保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。
※3 医療の必要性の高い方については、110円になります。
介護保険と医療保険の限度額が高額になったとき
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後、世帯内の被保険者全員で計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合、申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合、または合算した自己負担額から次の表を超えた金額が500円以下の場合は、支給されません。
| 世帯区分 |
限度額(年額) |
|---|---|
| 現役並み3 | 212万円 |
| 現役並み2 | 141万円 |
| 現役並み1 | 67万円 |
| 一般2 | 56万円 |
| 一般1 | |
| 区分2 | 31万円 |
| 区分 1 | 19万円 |
※支給対象となる方には、翌年3月から4月頃に福島県後期高齢者医療広域連合よりお知らせを郵送しますので、申請してください。
※新たに後期高齢者医療制度に加入された方など、支給申請のお知らせを送付できない場合があります。
各種申請・手続きについて
資格確認書等の再交付について
資格確認書等を破損・紛失した場合には、手続きをすることで再交付を受けることができます。
申請に必要なもの
- (様式第6号の2)資格確認書等再交付申請書 [PDFファイル/86KB]
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【代理人が申請する場合】
- (様式補助)委任状 [PDFファイル/53KB]
- 代理人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※なお、観光課(裏磐梯合同庁舎)で手続きをした場合は、資格確認書の即日交付はできませんので、後日郵送にてお届けします。
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
高額療養費制度における限度額の適用について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月1日をもって「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の発行が終了しましたが、申請に基づき世帯区分が記載された資格確認書を提示することで、窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。対象となる方は、「自己負担割合が3割で住民税課税所得が690万円未満の被保険者がいる世帯の方」、または「自己負担割合が1割で住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方」です。
なお、マイナ保険証を提示することで世帯区分が記載された資格確認書の提示は不要となります。
申請に必要なもの
- (限度額適用の場合)(様式第6号)資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/145KB]
- 後期高齢者医療資格確認書
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
【代理人が申請する場合】
- (様式補助)委任状 [PDFファイル/53KB]
- 代理人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※なお、観光課(裏磐梯合同庁舎)で手続きをした場合は、限度額区分が記載された資格確認書の即日交付はできませんので、後日郵送にてお届けします。
高額の治療を長期間受ける必要があるとき
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病がある方は、申請により限度額が1万円(月額)となる「特定疾病療養受療証」を交付します。
※申請により、特定疾病区分を記載した「資格確認書」の交付を受けることもできます。
※特定疾病の認定を受けた場合は、マイナ保険証を利用して受診する際に、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の窓口での提示は不要となります。
厚生労働省が指定する特定疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 特定疾病に該当していることを確認できる書類(医師の診断書など)
- 後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)
- (様式第28号)特定疾病認定申請書 [PDFファイル/112KB]
葬祭費について
被保険者が亡くなられたときには、申請により葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書 [PDFファイル/146KB]
- 亡くなられた被保険者の後期高齢者医療資格確認書
- 喪主の確認ができるもの(会葬礼状など)
- 喪主の方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 喪主の方の口座番号と名義人の確認ができるもの(預金通帳など)
年に1度、健康診査を受けましょう
後期高齢者健康診査は、病気や持病の重症化や加齢に伴う心身の衰え(フレイル)を防ぐために大切な健診です。健康長寿のため、年に1度は健診を受けましょう。
詳しくは
福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>